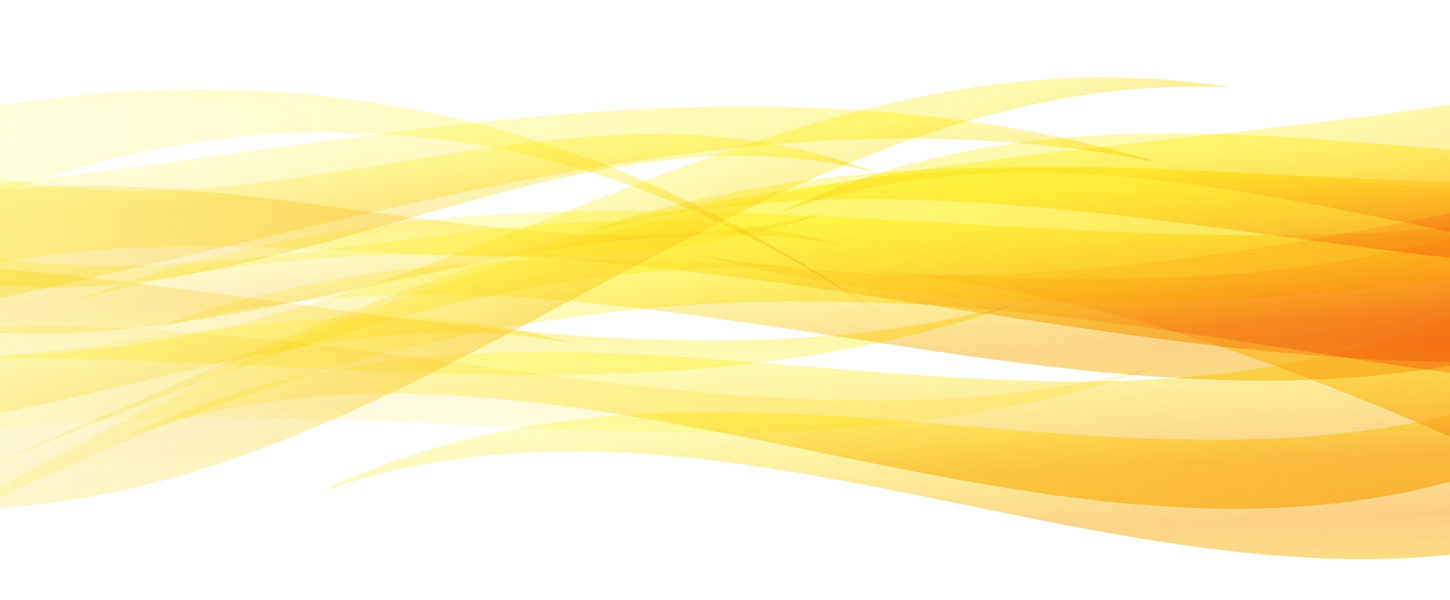「KY」より怖い「黙る」という選択
ISDエデュケイションズの服部真人です。
今月のコラムは
空気を読むな!流れを読め。
先日、あるミーティングで興味深い出来事がありました。新しいプロジェクトの方向性について議論していた時、一人の女性が「それは違うと思います」と発言したのです。一瞬、場が凍りつきました。でも、その意見がきっかけで議論が活性化し、最終的には全員が納得できる内容にまとまったのです。
この出来事を見て、私は孔子の「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」という言葉を思い出しました。
「空気を読む」ことが過度に重視される今の時代で、あえて異論を唱える勇気の大切さ。今回は、2500年前の孔子の言葉から現代を生きるヒントを探っていきたいと思います。
「KY」より怖い「黙る」という選択
「空気読めない」と烙印を押されることを避けるあまり、自分の意見を飲み込んでしまった経験はありませんか?
会議で異論があるのに黙る、周囲と違う意見があっても口をつぐむ、本当は反対なのに賛成のふりをする…。これらは全て「黙る」という選択の症状です。
孔子はこんな現代人を見たら、きっと溜息をつくでしょうね。
想像してみてください。
タイムスリップした孔子が渋谷のスクランブル交差点に立っています。スマホを見ながら同じような服装で歩く若者たち、同じようなハッシュタグを使い、同じようなポーズで写真を撮る人々。
孔子はつぶやくでしょう。「小人は同じて和せず」と。
同じことをしているように見えても、それは表面的な同調に過ぎず、真の調和ではない。インスタのフィルターのように、皆が同じ色調で写っているだけで、本当の意味での「和」ではないのです。
「和」と「同」の違い、あるいはオーケストラとカラオケの違い
「和して同ぜず」の真意を理解するには、オーケストラとカラオケの違いを考えるとわかりやすいかもしれません。
オーケストラでは、各楽器が異なる音色、異なるパートを持ち、それぞれの個性を発揮しながらも美しいハーモニーを生み出します。これが「和して同ぜず」です。
一方、カラオケの採点機能は原曲にどれだけ「同じ」に歌えるかを競います。個性的な歌い方をすれば採点は下がる。これが「同じて和せず」の世界です。
あなたの職場や家庭は、オーケストラですか?それともカラオケ採点マシーン?
【実践編】あなたも「君子」になれる
「和」を装った「同調圧力」の見分け方
「これは協調性のためだ」と言いながら、実は単なる同調圧力であることは多々あります。見分けるポイントをいくつか挙げてみましょう。
1.理由が説明されない:「みんなそうしてるから」「昔からのやり方だから」という説明しかない
2.反対意見を言うと人格否定される:「協調性がない人だ」「空気読めない」と批判される
3.結果より過程が重視される:やり方が違っても結果が良くても評価されない
4.異質なものへの恐怖がある:「前例がない」が最大の拒否理由になる
これらが当てはまる環境では、「和」を装った「同」が幅を利かせている可能性が高いでしょう。
「君子」になるための現代的実践法
では、現代社会で「君子は和して同ぜず」を実践するには、どうすれば良いのでしょうか?
1.自分の「譲れないもの」リストを作る
全てに妥協する必要はありません。自分にとって本当に大切な価値観や信念は何か、明確にしておきましょう。それ以外は柔軟に対応できます。
2.「建設的反対」の技術を磨く
単に反対するのではなく、「こうすればより良くなるのでは?」と提案を含めた反対意見を述べる技術を身につけましょう。
3.「場」と「タイミング」を選ぶ
全員がいる公の場で反対するより、事前に個別に伝える方が受け入れられやすいこともあります。戦略的に考えましょう。
4.多様性を積極的に評価する習慣をつける
周囲の人の「違い」を欠点ではなく、チームの強みとして捉える視点を持ちましょう。
5.「同調バイアス」を定期的にチェックする
自分が本当にそう思っているのか、ただ周りに合わせているだけなのか、時々立ち止まって考えてみましょう。
【調和とは「和音」であって「単音」ではない
孔子の「君子は和して同ぜず」という言葉は、2500年の時を超えて、むしろ現代社会においてこそ重要な意味を持ちます。
真の調和とは、全員が同じ音を出すことではなく、異なる音が響き合って美しい和音を奏でることです。それは職場でも、家庭でも、SNSでも同じこと。
「空気を読む」ことに疲れたなら、「流れを読む」ことを始めてみませんか?空気は同調を求めますが、流れは自然に進みながらも大きな調和を生み出すものです。
孔子も言うでしょう。「いいね」より「いい流れ」を作れと。